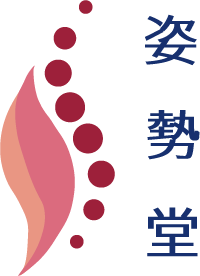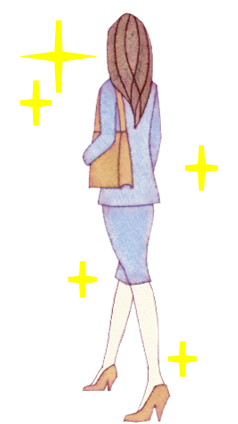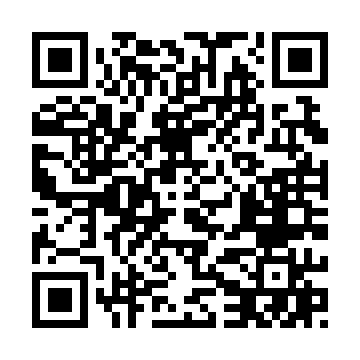ブログ

日本の風物詩「お盆」
- 2021/08/11
- 日常
みなさんこんにちは(^^♪
オリンピックも無事に終わり、
歴代最高のメダル数も獲得し
次はゆっくりお盆休みへと突入ですね。
お盆と言えば
ゆったりとご先祖様をお迎えして
楽しく過ごすのが常ですが、
実際に「お盆」とはどういう事をする
風習なのか知っていますか?
まず一口に「お盆」と言っても
地域によって期間が若干異なります。
広い地域では
8月の13~16日の4日間がお盆としています。
ですが東京都市部や一部の地域は
7月の13~16日であったり、
沖縄や鹿児島の奄美地方では
旧暦にのっとって定める為年毎に異なりますが
大体7月の13~15日の3日間だったりします。
元々は仏教の「盂蘭盆(うらぼん)」が由来であり、
餓鬼の世界に落ちた母を救うために
食べ物や飲み物等様々な物をささげ救ったことから
来ていると言われています。
このことからお盆は先祖供養の行事として残ったと
言われています。
また一般的には
お墓や仏壇の掃除・盆提灯の飾りつけを行い、
ご先祖様を迎える「精霊棚(しょうりょうだな)を
用意します。
この棚にはキュウリで作った精霊馬、
ナスで作った精霊牛を飾ります。
この2つはご先祖様が家とあの世を行き来する際に
使用する乗り物だそうです。
ご先祖様が早くこちらに来て
ゆっくりと過ごしてもらえるように
準備して迎えしょう(*^_^*)